実は私は、戦争がテーマの映画は好きではなかった。そういう悲惨な場面は見たくなかったからだ。でも、ここ最近で、最も強烈に心動かされた物語は、以前触れた『ラーゲリより愛を込めて』であり、またこの『永遠の0』だった。『永遠の0』は、特に原作の本から、”ただ生きてるだけじゃだめなんだ”という真剣なメッセージを受け取れた。
今を生きる日本人への希望と警告をくれる、とても貴重な作品だ。この本が400万部近くも売り上げたのは、ただ家族愛に泣けるから、という理由だけではないと思う。
私は、この本で語られる戦争体験談の内容を最近のニュースに照らし合わせて、ハッとした。何だか似ていたからだ。一方で、人がこんなにも深く家族を思える力と、家族のみならず、仲間、国、さらには敵、故人のことまでも思える大きな心に感動した。ここまで、大きく深い愛をもてる人には、現実世界ではなかなか出会えないからだ。
最後には、改めて、「人の世界は、光と闇と両方で、できているものなんだな」と腑に落ちた。こういうところも、とても面白かった。
宮部さんの2つの謎
この物語は、主人公が祖父にあたる宮部さんのことを知るために、彼に関わったことのある人々を訪ね回る形で進められる。そして、戦死した宮部さんの情報を集めていくと、宮部さんの生き方には2つの謎が浮かび上がる。
一つは、戦場で逃げ回る”臆病者”と呼ばれていたのに、戦闘機の操縦の腕はピカイチだったこと。もう一つは、ずっと「絶対に生きて帰る」と言っていたのに、最後は特攻隊に志願して戦死したこと。
一つ目の謎解き ~「臆病者」でいた理由~
一見、怖がりで自分のことしか考えない人にもとれる。しかし、神がかった技を繰り出せるほどの腕があったから、やろうと思えば一人で敵を大量にやっつけられたはずだ。実力があり、強いのだ。怖がってはいなかっただろう。ではなぜ、戦うことを回避し続けたのか?
それは、絶対に死なないためだ。自分が死ぬことで、妻と子に悲しさ、生きる上での不自由さ、貧しさを味わわせないため。自分の他に誰も代われない、夫と父親という役目を果たしてあげたいという深い愛情によるもの。
また、むやみに人を殺さないためだ。人の命を尊く思う気持ちが人一倍強かったから。きっと、殺し合いの戦争には反対だっただろう。積極的に敵を殺したいとも、自分や仲間が殺される危険を冒して戦いたいとも思えなかったのだと思う。
その為には、宮部さんは、戦闘機の操縦技術や危機察知能力を最高度まで高める必要があったのだ。敵のアメリカの戦闘機とは違って、日本の戦闘機は盾になる強度がなく、一発撃たれたら、すぐ命を落としてしまう構造だった。だから、一回もミスできなかった。物凄い緊張感、プレッシャー、鍛錬の凄まじさだっただろう。
それすら乗り越えた、宮部さんの妻子への愛の強さ、人の命を大切にする思いの強さに感動させられる。自分のこと以上に、他者を思う人間だけが起こせる奇跡の一つだと思う。誰かを救いたいと思う力には、無限の可能性が発揮されるんだなと思った。そういえば、漫画のヒーロー達もそうだ。

宮部さんはまた、周りの仲間にも自分の命を大切にすることを強く説いた。「自分だけの死じゃない。自分がなくなることで悲しむ人のことも思え」と。「国の為に命を捧げろ!」という圧の強かった世の中、軍隊生活の中で、普通はそんなことを口にすることも、考えることも阻まれる状況だ。なかなかできたものじゃない。
さらに、生きて帰った後、何がしたいか、希望を描くように投げかける。戦争が終わった世界で、自分の夢を思い描いてみては?と。
誰もが目の前のことで精一杯になり、死と背中合わせの厳しい現状にのまれてしまうものだ。そんな中でも敢えて、この先の希望を想像しようとすること。一見、無意味に思えるだろうが、実はこの発想がきっと必要だと最近学んだ。人間の力の及ばないような力を動かせるとしたら、この発想なのだと。叶う!という思いだけが状況を好転させ得ると。絶対無理と思っていては、無理な現実しか来ないだろう。
宮部さんは、きっと、その時代には変人扱いされ、疎まれたと思うが、どの時代にあっても変わらない、”人間として最も大切なこと”を守り抜いた生き方だ。とても美しい。

二つ目の謎解き ~特攻隊を選んだ理由~
二つ目の謎解きは、難しかった。なぜ、特攻隊になって死んでしまったのかは、なかなか分からなかった。もちろん、もう妻子のことはどうでもよくなったからではないことは分かった。でも、妻子の為、生きて帰るという強い気持ちをしのぐ程の、どんな大きな思いが出てきたのかが分からなかった。そこで、印象的だった映画の最後のシーンと、本の最後のシーンについて考えていたら、納得のいく答えが出せた。
映画の最後に、特攻隊で空母に突っ込む寸前、宮部さんはうっすら笑みを浮かべる。そして、本の最後では、空母に激突して亡くなった宮部さんを、なんと敵のアメリカ兵の皆さんが敬意をもって水葬する。
アメリカ兵の皆さんは、ここまでたどり着いたのは神業だと。人間にできることじゃないと宮部さんの凄まじさに敬意を表した。また、ポケットに入っていた妻子の写真を見て、人としての彼の死を悔んでくれた。そして、宮部さんの遺体を大切に白い布で包んで、弔銃をならして、弔ってくれたのだ。敵であっても
亡くなった後の人にも、深い思いを向けられるのは、人間性の素晴らしいところだと思う。このように、敵であっても、戦って亡くなった宮部さんに思いを寄せるのだから、戦死したたくさんの仲間達へ向けた宮部さんの思い、弔いたい気持ちは、とても大きくなっていたのではないだろうか?

それを踏まえると、私はこう考える。
多くの戦死した仲間達に対する、人の為に命を懸けて戦い抜いたことへの敬意、また、彼らの抱えた無念さを少しでも癒したいという気持ちから、彼らを弔うために特攻隊になったのだと。弔うとは、死者を悲しみ悼むこと、死者の霊やその遺族を慰めること、敬意や感謝を示すこと。
特攻隊として戦死した仲間達は皆、空母への突撃を叶えたくて命を懸けた。しかし、誰も叶わなかった。宮部さんにはそれができる可能性があったから、自分が叶えることで、無念を晴らそうとしたのではないだろうか。
例え、宮部さん一人が空母へ激突したところで、この戦争は終わらず、また、勝利に導くことなど到底できないと分かっていただろう。だから、現実的に意味はなかった。そうだとしても、仲間への自分の思いから、それに意味をもたせたかったのだと思う。
自分が空母激突を果たせば、これまでゲームのように撃ち落されていった仲間達、兵器の一部のように扱われて自爆を強いられた仲間達の無念さは、少しは晴らせるだろうと思ったに違いない。そして、特攻隊を命じた人、この戦争をやめさせなかった人達に、特攻隊一人空母に突撃しても意味はないことを知らしめようとも思ったかもしれない。「もう戦争をやめてくれ!」という意思表示にもしたかったのかもしれない。
空母への突撃直前に、宮部さんは薄っすら笑みを浮かべる。なぜ、こんな死ぬ間際に笑えたのか?それは、自分の実力の全てを出し切っても、万に一つの確率だった、空母への到達が成功して、ホッとしたからだと思う。そして、「よかった!命を懸けた甲斐があった!」と喜んだ笑みに思える。また、先に亡くなった仲間達が「ありがとう!」と言ってくれる声が、たくさん聞こえていたからかもしれない。
宮部さんの思いをつなぐ人々
宮部さんはその生き様で、”願う生き方”を体現できている。宮部さんは、「”一人一人の人間の命”、”幸せな生き方”を尊重したい」という思いをもち続けて、それにのっとった生き方をやり遂げた。そういう人の心の美しさに共鳴して、周りの人も、その思いをつないで、その生き方をし始める。そして、その輪が広がると、奇跡は起きて、望む現実を引き寄せていける。
「生き抜け!」と教わった人達は戦後も生き抜き、幸せに暮らしたのだ。戦時中、誰もがあきらめていた幸せを引き寄せた。また、宮部さんの悲願だった妻子の幸せについては、生き残った仲間達が叶えてくれた。
「愛ある信念を貫く人の生き方が、何人もの生き方を変え、世界を好転させる力がある」ということを伝えてくれている。キレイごとだとする嫌悪感は手放そう。綺麗なものはいいじゃない。
今、戦時中に比べてみれば、生死の制限なんて感じず、物の豊かな世の中に生きている。でも、人々の心に潤いはなく、未来への楽しみは少なく、人を思う気持ちは薄れている。自分のお金と保身に目一杯で、物で心を満たそうとするからだ。この現状を好転させるには、「愛ある信念を貫ける人」を私達も目指し、また、そういう人を育てること。出来なくはないと、宮部さんはエールを送ってくれているだろう。
当事者の体験から教わる、日本の戦争のホント
この本はとても分厚く、そのほとんどが戦争体験が詳細に語られている場面だ。物語の後半に差し掛かったころ、いろいろな立場で戦争に関わっていた人達の語った”戦争”が重なり合っていき、”日本の戦争のホント”が浮かび上がってくる。
この物語はフィクションだが、「どうやって戦争する流れになったか?」「多くの戦いがどのように進み、何が勝敗を分けたか?」「戦っていた人は、どんな状況だったか?」を分かりやすく伝えてくれている。
学校の歴史の授業で習ったり、テレビで見聞きしたりした内容とはまた違い、より具体的で、過去の反省を活かす為に必要な内容が読み取れた。だから、今を生きる私達への警告だと感じたのだ。

戦争の流れから、分かったこと
まず、世の中は不景気で、若者の経済的自立が困難な状況だった。貧しさ、将来への不安から逃れるため、軍隊に入る人が多かったようだ。「このまま働いていても、これ以上お金が稼げる見込みはない。貧乏から抜け出せそうにない。だから、軍隊に入ろう」という若者の流れがあったようだ。
そこに、「戦争して戦うことは素晴らしいこと」と意識させるような政府、メディアの様々な宣伝が行われた。世の中では、戦争に行く兵隊さん達は、”英雄”として憧れられる存在とされていった。東大に入る人がエリートとして憧れられるのと同じように。
こうして、兵隊になる人が集まり、世の中の人達が戦争したほうがいい!と思う様になった。戦争の準備完了だ。
戦時中は、実際に戦う人達のことは正しく伝えず、国民がもっと戦ってくれ!勝ってくれ!と思い込むように、メディアが報道していった。また、政府の圧力によって、戦争を反対するような言論は許されなくなっていった。
最終的には、本土の武器を持たない国民たちを守る兵がいなくなっても、戦うことをやめなかった。兵隊や本土の国民の食料が尽きてきても、武器や燃料が足りなくなっても、戦い続けた。大空襲を散々受け、核兵器も落とされた。そして、ようやく降参した。
つまり、政府はすぐに国民の命を守る選択をしなかった。
降参した後は、また、メディアを使って、今度は戦争したのは悪いことで、その責任は政府ではなく、戦っていた兵隊さん達が負うものだと報道した。アメリカの指示もあっただろうが、今までの真逆の宣伝である。
そのせいで、国のために命を懸けて戦って、命からがら帰って来た兵隊さん達は「戦争した犯罪者」というレッテルを貼られて、疎まれ、住む土地を追い出された人もいたようだ。なんということだろう。「戦うことは素晴らしい」とする政府からのポスターも、すぐ回収命令が出て、全国から回収され、隠蔽された。何事もなかったかのように。
経済的な不安、死の恐怖、プロパガンダ(政府の圧力)、マスコミの情報操作によって、国民全体が戦争しようとする流れを作る。次に、敗戦事実の隠蔽によって批判を避け、多くの国民が死んでしまう事態を、知らない間に推し進めてしまう。最後は、都合よく責任転嫁、責任逃れをして、事実をうやむやにするため、また、マスコミの情報操作を利用する。
この流れ、現代社会でも、どこかで聞いたような気がしないだろうか?
戦った人達だけが知る、勝敗の要因 ~組織のトップは現場を知らない~
太平洋戦争での数々の戦いが、いろんな人に語られる中で、共通点が浮かび上がる。
それは、軍隊は階級制になっていて、そのトップにいるリーダー達は皆、実戦経験の乏しい東大出のエリートだった、ということ。また、そのリーダー達は、戦いに勝つことよりも、自分達の出世を第一に考えたような戦い方をしたり、実戦経験を積んだ者たちの見解を無視した軽弾みな策に出たりした為、多くの犠牲を出して敗戦する流れになったこと。
国を守るためにみんなで力を合わせて頑張ろうとしている若者達の命を全く顧みずに、トップに立った人間達は国も国民も頭になく、自分達の利益ばかり気にして動いていたということだ。もちろん、人の命を大事にしたリーダーもいただろうが、そうではないリーダーが多かったのだ。
気付けば多くの人が反論もできない、怒涛も組めない、助けを求める当てもない、手も足も出ない状況に追い込まれていた。大勢の犠牲が目に見えていても救えない状況だった。この場合、ただ、優しく従順なだけの人では太刀打ちできない。上の立場には従うもの、自分の意見をもつものじゃない、という人ばかりでは歯が立たない。東大出のエリートら、学歴の高い者が一番価値がある、逆に学歴の低い人は価値がないという固定概念の人達も、この流れにのまれていくだけだろう。
では、”大勢の犠牲が目に見えていても、誰も救えない状況”にしないためには、どういう人間がたくさんいないといけないのか?それを、みんなで考えるべきだ。
こういう状況のピラミッド型構造を、今なお、日本社会で、目の当たりにしていないだろうか?
もし、戦争にならない世の中にするなら…

戦争にならないようにするには、この社会がどうあるべきか?と考えてみる。まず、不景気という流れなどで、多くの人が生きることへの不安や恐怖を煽られる時が要注意だ。冷静な判断がつかなくなり、我先にと、”安心・安全”という宣伝に飛びついてしまう。
また、この宣伝とは、テレビ・ラジオ・新聞などで、政府が一方的に流す情報が多い。それは、事実かどうか、疑ってかかり、他の発信者による情報とも比較してみる力が必要だろう。今は、国民の側に立って発信するユーチューバーたちがいる。国民一人一人が発信できるツールがいろいろある。世界視点の情報も、得やすい。それらを活用して、自分が信用できる情報を集めることが大事だ。
そして、国民全体に関わることを決める人に、もっと人間性の高さを求める社会にしていくこと。自分の見栄や出世、お金だけを求める社会では、そういうトップの人しか出てこない。やっぱり、国民が自分だけ、お金だけという価値観で生きていては、みんなのことを思い、生き方をも大切にするリーダーなんて育たないのだ。その上、弱いものを虐げても仕方ない、というような風潮に自然となる。学校のいじめも、世界の戦争も、この人の意識の根源から生まれる。
人の命が理不尽に奪われるような世界は間違っている。人の精神が理不尽に傷めつけられるような関係性は間違っている。そんな現実を見たなら、何かおかしいと感じなければならない。普通ではないと。そして、そのまま続けず、一旦立ち止まって、変えようと考える必要がある。今、本当に大切にすべきものは何か?を心で感じ直すべきだ。
周りに流される人、今までの固定概念にハマったままの人がほとんどである中、そうできる人はなかなかいない。宮部さんの様な人がなかなかいなかったように。それでも、一人踏み出せることで、希望が始まる。
『永遠のゼロ』から感じ取る光と闇
あらがえない程の闇。お金と権力を使って我欲に走る人々が、他の多くの人をいいように操る世界。そんなことを想像すると、あきらめて、見て見ぬふりをして、自分も目の前の我欲を満たすことに逃げたくなる。でも、それでは、幸せがこない。だから、違うんだ。
我欲は誰にでもある。恐怖や不安には弱い。やられたらやり返したくなる。それが人間だ。ということは、闇があるのが人間世界。光だけになんて、できないもの。
その前提で、私はどう生きたいか?を試すのが人生。私はどんな光の存在を目指したいか?人とどんな幸せを味わいたいか?それを、心から偽りなく、考えて、一人一人で実践するのが人間なんだな、と分かった。
みんなが同じように思ってくれないと怒ってやめるのではなく、見返りに頼らず、自分がそう生きたいからそうするだけ。与えられた状況で、精一杯、自分の本当に望む幸せを求めて生きる。闇はあって当たり前。でも、光が好きなら自分はそっちを向けばいい。そうは分かっても、なかなかに強さがいる生き方だな。

タイトルの意味
宮部さんのゼロ戦は、過去に戦死した人たちの思いを乗せて、未来にあたる、今を生きる人々にそれをつないでいる。つまり、時空を超えて、思いを運び、存在し続ける。だから、”永遠”と名付けられたと思った。
また、永遠に”ゼロ戦”=”特攻隊”=”命を投げ捨てる戦争”はゼロでなければならない!という強いメッセージでもあるかもしれない。
ただ生きてるだけじゃだめなんだ。闇に動かされないように闇を知り、光を増やせるように光を探して生きていこう。愛ある信念を貫く人の生き方が、世界を好転させ得る。

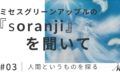
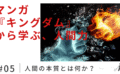
コメント